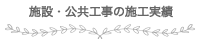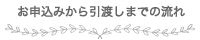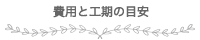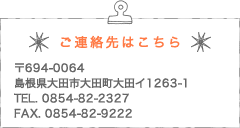住宅の施工事例
新築
匠の技
家主のこだわりと匠の技

伝統の知恵や、先進的な住宅の技術、良質な素材をいかし、設計からデザイン、環境への配慮にいたるまで、最上級の暮らしをご提案します。

玄関は、その家の顔です。扉を開けて中にはいると、それぞれの家の個性的な空間が現れます。お客様を迎えたり、家族を送り出したり、時には、ペットがお出迎えすることもあります。住まいの第一印象が決まるところでもあります。
お化粧にもその時代の流行があるように、お客様をお迎えする玄関のスタイルにも流行があります。もっとも目につきやすい場所だからこそ、玄関にもさりげないこだわりとセンスを出していくことで、お客様からの印象がよくなります。
お化粧にもその時代の流行があるように、お客様をお迎えする玄関のスタイルにも流行があります。もっとも目につきやすい場所だからこそ、玄関にもさりげないこだわりとセンスを出していくことで、お客様からの印象がよくなります。
個性的な空間

さまざまな加工や造作をして仰々しい感じがでるよりも、現在は、自然の素材感を出しつつも、まとまりのあるシンプルなスタイルをベースにそれぞれのこだわりを出していかれる方が多いようです。
シンプルでありながら、基本がしっかりしているからこそ表現できる美があります。檜の引き戸を用いた和風の玄関から、開放感溢れる吹き抜けを用いた洋風の玄関まで、家主様のこだわりを匠の技で表現し、安心と同時に、住まう人の感性を豊かにして、心地良いライフスタイルへ導きます。
また、平屋でありながらリビング・ダイニングを開放的な空間とし、スペースの有効活用として、ロフトを設けるとともに、なるべく自然の明かりを取り込むために、浴室前には天窓を設置しました。
シンプルでありながら、基本がしっかりしているからこそ表現できる美があります。檜の引き戸を用いた和風の玄関から、開放感溢れる吹き抜けを用いた洋風の玄関まで、家主様のこだわりを匠の技で表現し、安心と同時に、住まう人の感性を豊かにして、心地良いライフスタイルへ導きます。
また、平屋でありながらリビング・ダイニングを開放的な空間とし、スペースの有効活用として、ロフトを設けるとともに、なるべく自然の明かりを取り込むために、浴室前には天窓を設置しました。
施主様こだわりのポイント
~日本が誇る歴史と伝統に裏打ちされた匠の技~
「格(ごう)天上」
格天井とは、日本や中国、台湾などで多く見られる、木材を使った伝統的な天井様式です。最も格式の高い天井様式といわれ、有名なお寺や神社、お城の天井に多く使われています。二条城二の丸御殿や日光東照宮外陣などの格天井が有名です。
和室の様式は、高い順に「真」・「行」・「草」の3つの格式に区分され、格天井は「真」の格付けにあたります。使われる場所は、和室、玄関、玄関ホー ル、廊下など多岐に渡り、一般住宅でも広く取り付けられています。
「風格ある化粧軒」
軒とは開口部への直射日光をさえぎり、外壁に雨がかからないようにするために、屋根の先端を外壁面からさらに外に伸ばした屋根の部分のこです。和風建築の軒裏や縁側などの天井は垂木(たるき)や野地板を化粧にして見せる「化粧軒裏」にしたものが多くあります。
軒先の高さは室内からの天空の眺めをさえぎる線ともなり、高さによって座敷の趣が異なります。軒先の仕上げには、軒裏の木をそのまま見せる化粧軒裏、軒裏に天井を張る軒天上、木部に漆喰を塗る塗り込め軒があります。蒸し暑い日本の夏に適合し、外部空間を深い軒の出で保護し、気温上昇を緩和します。
「格(ごう)天上」
格天井とは、日本や中国、台湾などで多く見られる、木材を使った伝統的な天井様式です。最も格式の高い天井様式といわれ、有名なお寺や神社、お城の天井に多く使われています。二条城二の丸御殿や日光東照宮外陣などの格天井が有名です。
和室の様式は、高い順に「真」・「行」・「草」の3つの格式に区分され、格天井は「真」の格付けにあたります。使われる場所は、和室、玄関、玄関ホー ル、廊下など多岐に渡り、一般住宅でも広く取り付けられています。
「風格ある化粧軒」
軒とは開口部への直射日光をさえぎり、外壁に雨がかからないようにするために、屋根の先端を外壁面からさらに外に伸ばした屋根の部分のこです。和風建築の軒裏や縁側などの天井は垂木(たるき)や野地板を化粧にして見せる「化粧軒裏」にしたものが多くあります。
軒先の高さは室内からの天空の眺めをさえぎる線ともなり、高さによって座敷の趣が異なります。軒先の仕上げには、軒裏の木をそのまま見せる化粧軒裏、軒裏に天井を張る軒天上、木部に漆喰を塗る塗り込め軒があります。蒸し暑い日本の夏に適合し、外部空間を深い軒の出で保護し、気温上昇を緩和します。